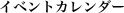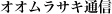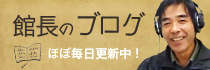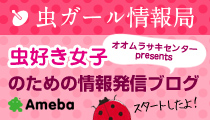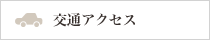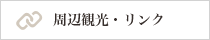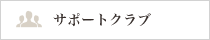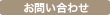- トップページ
- オオムラサキについて
| オオムラサキは、昭和32年に日本昆虫学会において、世界に誇る日本の代表的な、格調高い華麗な蝶として国蝶に決まりました。オオムラサキは、羽を広げると10センチ以上になる大型のタテハ蝶で、雄は羽の表側が美しい紫色に輝き、雌ではこの紫色の輝きがありません。 成虫は6月下旬〜7月下旬にかけて羽化し、国内では北海道から本州、四国、九州に、国外では中国、ベトナム、台湾、朝鮮半島に分布しています。 |  |
オオムラサキの名前について
 オオムラサキ(タテハチョウ科コムラサキ族)
オオムラサキ(タテハチョウ科コムラサキ族)【学名】Sasakia charonda Hewitson(ササキア・カロンダ・ヒューウィトソン)
「Sasakia」は日本昆虫学の創始者ともいうべき「佐々木忠次郎博士」の名にちなんで、「charonda」は紀元640年頃、イタリアのシシリア出身で有名な立法学者「カロンダス」から、「Hewitson」はイギリス人ロバート・フォーチュンとヒューウィトソンによって世界に紹介されたことから、学名が付けられました。
国蝶になったのはいつ?
昭和31年(1956年)オオムラサキの記念切手が発行。昭和32年(1957年)日本昆虫学会で国蝶に選定されました。勇ましく、堂々としていて、華麗(気品のある美しさを持っている)である事と日本中に分布していることが理由にあげられています。
現在、環境庁では自然環境を測定する目安になる指標昆虫の一つにオオムラサキを選んでいます。
オオムラサキの特徴は?
 日本のタテハチョウ科の中では最大の大きさのオオムラサキ。翅を広げるとオスが約10センチメートル、メスが約12センチメートル、南に生息しているのものより、北に生息するものの方が小型です。翅の表面の色は、オスは青むらさき色、メスは茶むらさき色。翅の裏面の色は、南のものは白色となり、北にゆくほど黄色が強い。日本の中央あたりでは白色と黄色が混在する。オオムラサキセンター周辺では、白色型と黄色型とが混在する。翅を閉じているときれいな方の翅が見えないのでオオムラサキだと分からない人が多い。普通のチョウのように「ひらひら」とは飛ばず、はばたきが機敏で滑空するような飛び方をする。飛翔の速度は速い。(右写真:オオムラサキのメス)
日本のタテハチョウ科の中では最大の大きさのオオムラサキ。翅を広げるとオスが約10センチメートル、メスが約12センチメートル、南に生息しているのものより、北に生息するものの方が小型です。翅の表面の色は、オスは青むらさき色、メスは茶むらさき色。翅の裏面の色は、南のものは白色となり、北にゆくほど黄色が強い。日本の中央あたりでは白色と黄色が混在する。オオムラサキセンター周辺では、白色型と黄色型とが混在する。翅を閉じているときれいな方の翅が見えないのでオオムラサキだと分からない人が多い。普通のチョウのように「ひらひら」とは飛ばず、はばたきが機敏で滑空するような飛び方をする。飛翔の速度は速い。(右写真:オオムラサキのメス)
オオムラサキの生息場所
 九州から北海道までのほぼ日本全土に生息しているが、都市化が進み,雑木林が少なくなってきた事で現在では生息地が局地的で少なくなってきている。北限地は北海道浜益村(札幌市の北西) 南限地は宮崎県野尻町 西限地は鹿児島県出水市 国外では、中国、朝鮮半島、台湾に生息する。オオムラサキの生息地としては長坂町が日本で一番多いと言われている。昔から炭焼きが盛んで、炭の原料となるクヌギ林が多く残っていることや、八ヶ岳高原に流れる水辺にエノキが多く生えていること、冬は寒く適度に雪が降るため乾燥が少ないことなどの条件が重なり、国蝶オオムラサキの日本一の生息地となった。(右写真:炭焼きの様子)
九州から北海道までのほぼ日本全土に生息しているが、都市化が進み,雑木林が少なくなってきた事で現在では生息地が局地的で少なくなってきている。北限地は北海道浜益村(札幌市の北西) 南限地は宮崎県野尻町 西限地は鹿児島県出水市 国外では、中国、朝鮮半島、台湾に生息する。オオムラサキの生息地としては長坂町が日本で一番多いと言われている。昔から炭焼きが盛んで、炭の原料となるクヌギ林が多く残っていることや、八ヶ岳高原に流れる水辺にエノキが多く生えていること、冬は寒く適度に雪が降るため乾燥が少ないことなどの条件が重なり、国蝶オオムラサキの日本一の生息地となった。(右写真:炭焼きの様子)オオムラサキの生活
 幼虫時代は、エノキ、エゾエノキの木の葉を食べる。成虫時代は、クヌギ、ナラ、ヤナギなどの樹液を吸うが、腐った果実や動物の排泄物などの汁なども吸う。人と森とが深く関わり合っている里山のクヌギやコナラの雑木林に好んで棲んでいる。国蝶オオムラサキにとって、エノキとクヌギの雑木林は生命の源。
なぜなら、オオムラサキはエノキで産まれ、幼虫時代にはエノキの葉を食べ、蝶になるとクヌギの樹液を吸って生き、またエノキにたまごを産み、そしてエノキの近くで死んでいくからだ。人が雑木林に手を入れなくなると棲みにくくなってしまう。通常1年を一生とし、幼虫で冬を越し、夏に成虫(チョウ)になり(長坂町では7月が最盛期)、8月に産卵を終えると成虫は死んでしまう。
幼虫時代は、エノキ、エゾエノキの木の葉を食べる。成虫時代は、クヌギ、ナラ、ヤナギなどの樹液を吸うが、腐った果実や動物の排泄物などの汁なども吸う。人と森とが深く関わり合っている里山のクヌギやコナラの雑木林に好んで棲んでいる。国蝶オオムラサキにとって、エノキとクヌギの雑木林は生命の源。
なぜなら、オオムラサキはエノキで産まれ、幼虫時代にはエノキの葉を食べ、蝶になるとクヌギの樹液を吸って生き、またエノキにたまごを産み、そしてエノキの近くで死んでいくからだ。人が雑木林に手を入れなくなると棲みにくくなってしまう。通常1年を一生とし、幼虫で冬を越し、夏に成虫(チョウ)になり(長坂町では7月が最盛期)、8月に産卵を終えると成虫は死んでしまう。でも、つぎの命がまためぐっていく…。(右写真:樹液に群がるオオムラサキ)
オオムラサキの一生
オオムラサキの寿命は約1年。
夏にエノキに産み付けられた卵は、約6〜10日でふ化します。
ふ化したばかりの幼虫は1齢幼虫といい、以後、脱皮をするごとに2齢、3齢と進み、4齢幼虫で越冬します。
そして冬を越しエノキの葉が芽吹き始める4月中旬、活動を再開した4齢幼虫はエノキの葉を食べ、5齢幼虫、そして6齢幼虫(終齢幼虫)まで成長します。
十分に成長した6齢幼虫はエノキの葉裏でサナギになり、6月下旬頃から羽化が始まります。
成虫が見られるのは一年のうち、夏の間のわずかな期間です。
成虫はその間に交尾・産卵を行い、次の世代へと命を繋ぐのです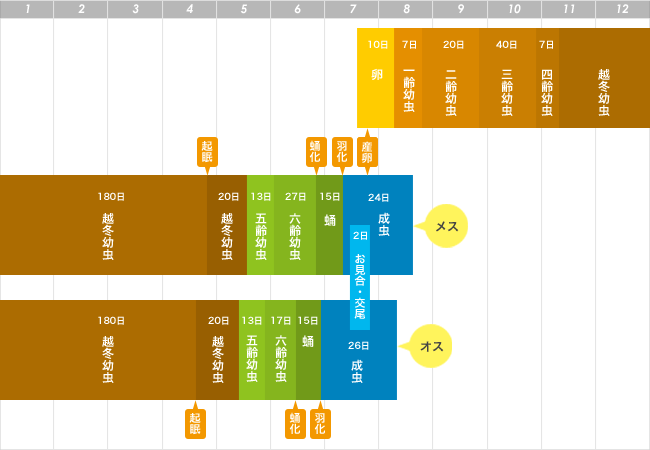















夏にエノキに産み付けられた卵は、約6〜10日でふ化します。
ふ化したばかりの幼虫は1齢幼虫といい、以後、脱皮をするごとに2齢、3齢と進み、4齢幼虫で越冬します。
そして冬を越しエノキの葉が芽吹き始める4月中旬、活動を再開した4齢幼虫はエノキの葉を食べ、5齢幼虫、そして6齢幼虫(終齢幼虫)まで成長します。
十分に成長した6齢幼虫はエノキの葉裏でサナギになり、6月下旬頃から羽化が始まります。
成虫が見られるのは一年のうち、夏の間のわずかな期間です。
成虫はその間に交尾・産卵を行い、次の世代へと命を繋ぐのです
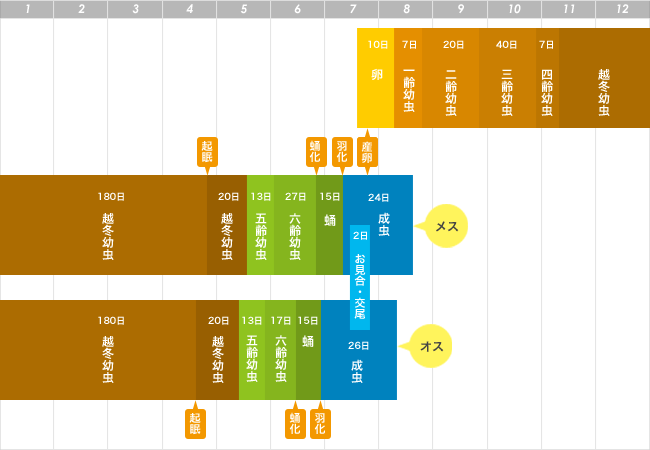
 |
卵卵の大きさは、直径1ミリメートル位ある。卵の上に精孔という穴があり、メスが産卵する時に精子がこの穴から入る。卵の縦のスジを縦条、横のすじを横条という。殻は固いキチン質からなり、空気は通しやすく水は通しにくくなっており、乾燥しないようになっている。 |
 |
一齢幼虫卵からふ化した幼虫は、卵のカラをほとんど食べてから、あちこちに散っていく。このカラ食べることによって、幼虫はエノキの葉を食べることを覚える。この頃はエノキの葉の真ん中に穴をあけるように食べる。頭には角はまだなくて、背中の突起物もあまりでていない。 |
 |
二齢幼虫一齢幼虫になってから一週間たつと一回目の脱皮がおこなわれ、二齢幼虫になる。頭に二本の角が出て、背中には4対の突起物がでてくる。ゴマダラチョウの幼虫はオオムラサキの幼虫とそっくりであるが、背中の突起物が3対しかない。ここ頃アリに食べられたり、脱皮中に死んだりして数が激減する。 |
 |
三齢幼虫二齢幼虫になってから20日間位たつと二回目の脱皮がおこなわれ、三齢幼虫になる。三齢幼虫になると、葉を端から食べるようになる。北海道、東北地方の寒い地域では三齢幼虫で冬を越すが、温かい地方では四齢幼虫で冬を越す。脱皮回数が一回少ない寒い地域のオオムラサキの成虫は小型のものが多い。 |
 |
越冬幼虫エノキの根元の落ち葉にはりついて冬を越す。温かい日には動き回ることがある。 越冬幼虫は、暑さと乾燥に弱いので、日中温度が上がらない日陰に固まっている場合が多い。 上:オオムラサキの幼虫(背中の突起物が4対) 下:ゴマダラチョウの幼虫(背中の突起物が3対) |
 |
起眠5月の若芽が芽吹く頃、越冬幼虫はエノキに登りはじめる。木に登った幼虫は、天敵の鳥などから身を守るため、枝の分かれ目の所にはりついていて、じっとしている。木に登ることができない幼虫も四割位いて、生存数が少なくなる。 |
 |
前蛹六齢幼虫が25日位すると六齢幼虫は葉の裏に台座を作り、頭を下にして、ぶらさがり蛹になる準備にはいる。これを前蛹という。このころカメムシに体液を吸いとられてしまうことがある。メスはオスより幼虫期間が10日位長いので、体は約3センチ大きくなる。これは卵を産むために必要なことである。 |
 |
羽化蛹の中で体が固まったところ(蛹になってから15日位)背中の部分が縦に割れて、成虫が頭から出てくる。殻から出たばかりの成虫はハネが伸びきっていないので、ぶらさがった状態で口と気門から空気を吸い込み、その圧力で体液をハネにおくりこんで伸ばす。 オスはメスより約10日ほど早く成虫になり、6月下旬から姿を見ることができます。 |
 |
交尾チョウの世界は、オスがメスを見つけ交尾をする。チョウは近視のため眼だけでは自分の仲間かどうか見分けにくい。樹液に集まるオオムラサキを見ると、触角で相手を確認する。この触覚の先に臭いをかぐ器官があり、オオムラサキのオスとメスであることを確認する。オスの尾に把握器とカギがあり、これを使ってメスと結合する。交尾時間は数時間かけないと受精しない。 |
参考文献
オオムラサキの詩 【文:高橋健 / 写真:三枝近志、堀田典男 / サンリオ】
オオムラサキの繁殖法 【著:森一彦 / ニュー・サイエンス社】
昆虫誌 【著:矢島稔 / 東京書籍】
飛べ オオムラサキ 【国蝶オオムラサキを守る会編 / 執筆:内城道興 / 写真:海野和男 / 講談社】
日本の蝶 【著:藤岡知夫 / 主婦と生活社】
オオムラサキの繁殖法 【著:森一彦 / ニュー・サイエンス社】
昆虫誌 【著:矢島稔 / 東京書籍】
飛べ オオムラサキ 【国蝶オオムラサキを守る会編 / 執筆:内城道興 / 写真:海野和男 / 講談社】
日本の蝶 【著:藤岡知夫 / 主婦と生活社】